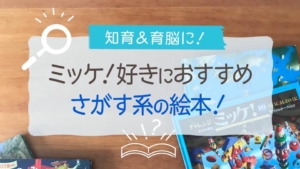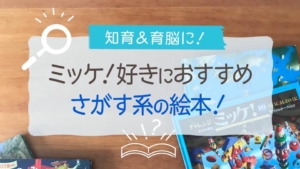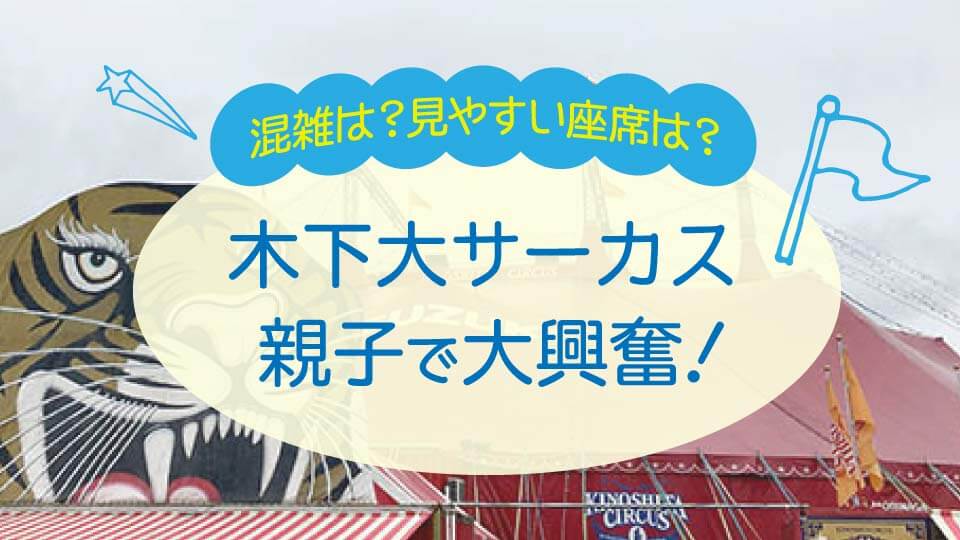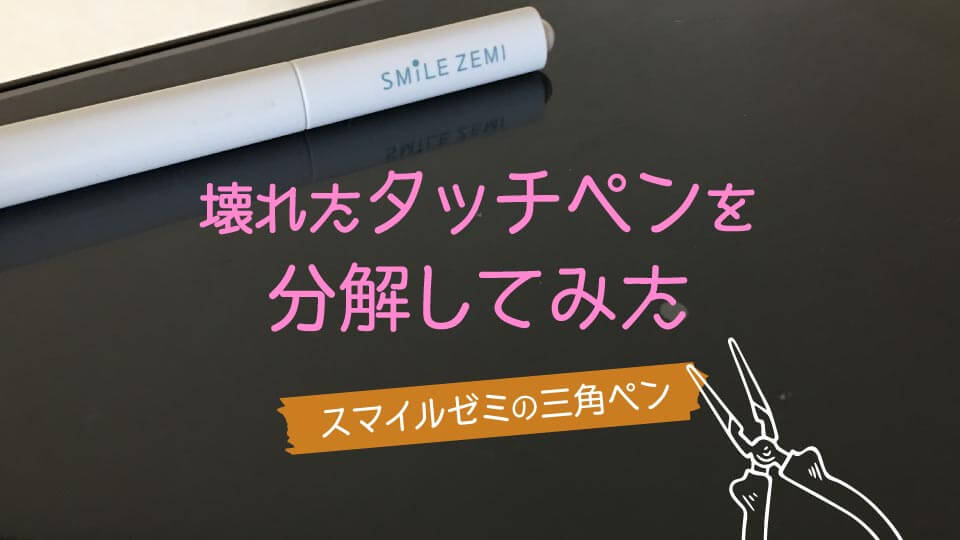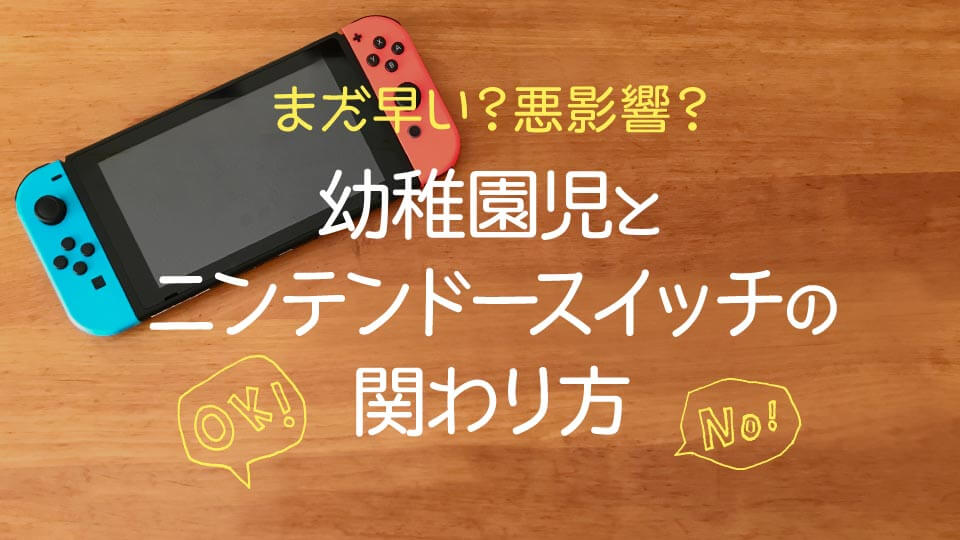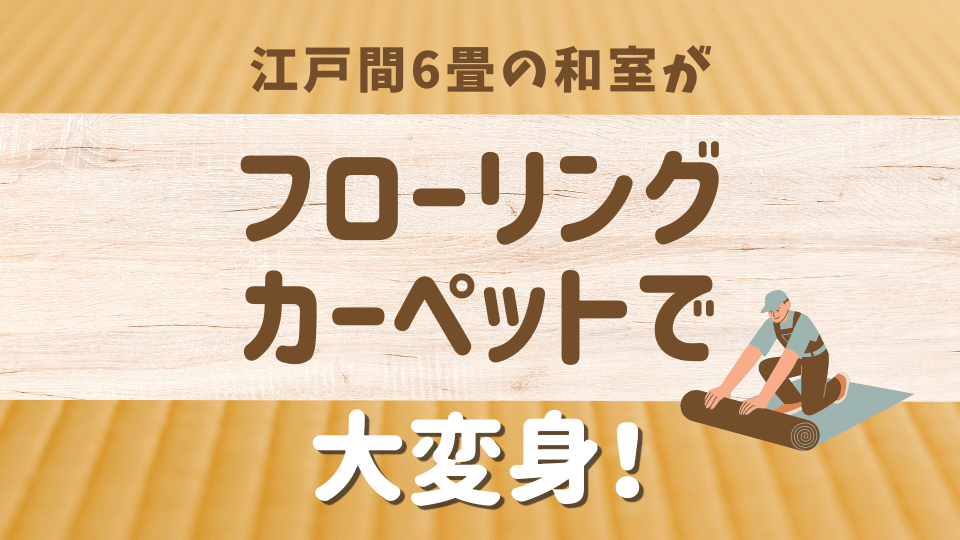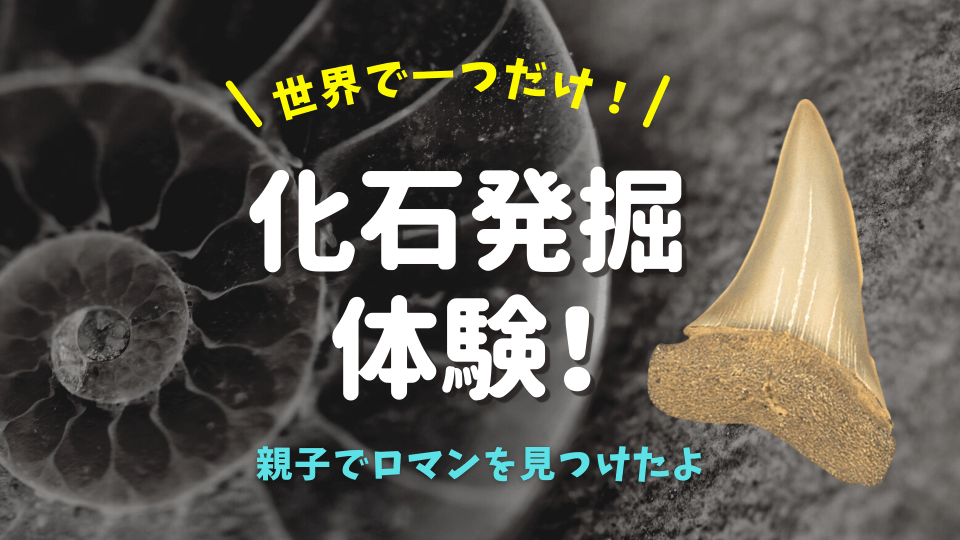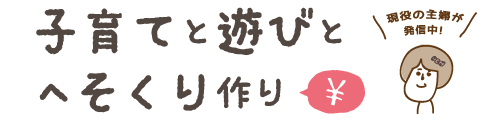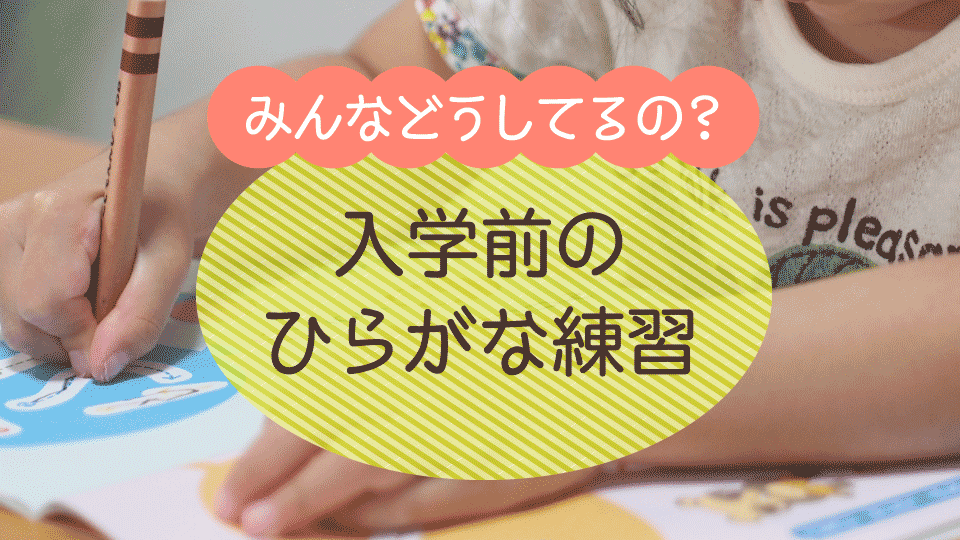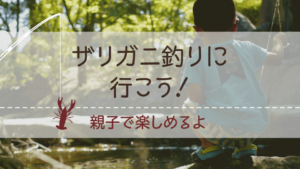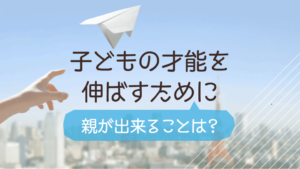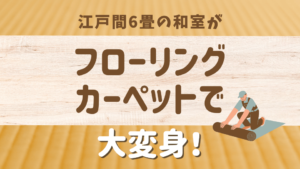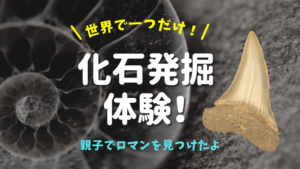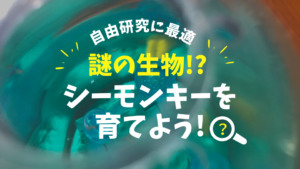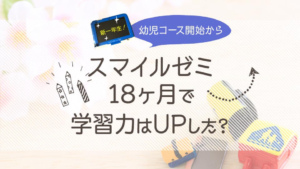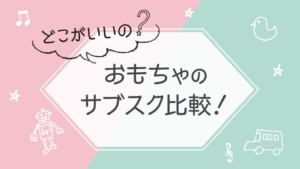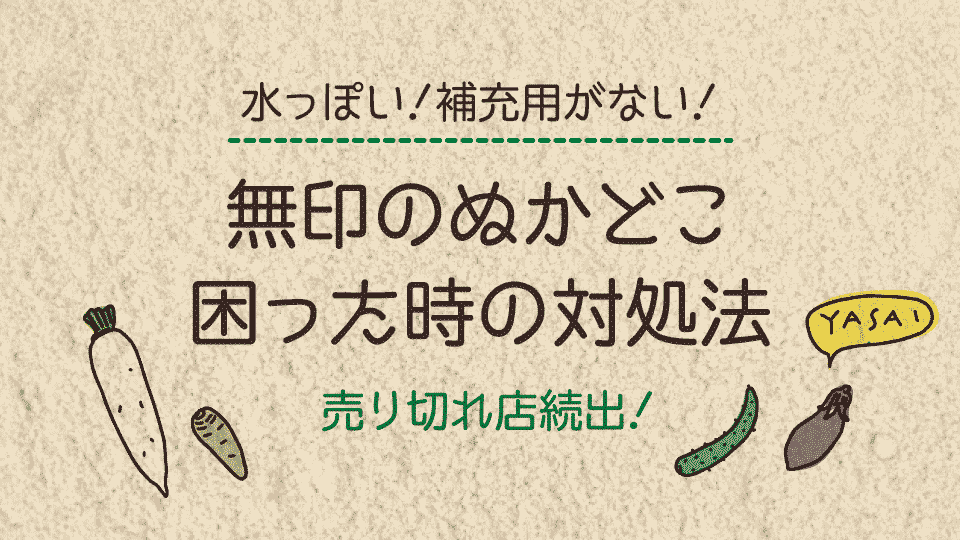ひらがなが読めない、どうしたらいい?
幼稚園の子どもを持つお母さんの悩みで多いのが、ひらがなの練習。
- 子どもにひらがなを覚えて欲しい
- ひらがなを覚えるにはどうしたらいいか
- 子どもがなかなか覚えず焦っている
- 小学校までには、ひらがなを読めるようになって欲しい
この記事を読むと、子どもが文字を読めるようになった方法がわかります。
幼稚園の時の実体験を書いていますので、ぜひ参考にしてみてください。
私は子どもが年少さんの頃、ママ友から「うちの子は、ひらがな読めるよ」と言われて焦った記憶があります。
でも、覚える時期もスピードも子どもそれぞれなんですよね。
焦らずのんびり向き合えったら読めるようになりました。
- 絵本で文字の形と読み方を一致させる
- かるた遊びをする
- ひらがな・カタカナカードで遊ぶ
- ひらがなポスターを生活に取り入れる
- 読めたら書く練習(ドリルやタブレットなど)
練習は何歳から始めたらいいか
まず、文字の名前を覚えることから始めました。え?それってどういうこと?って思いますよね。
幼い子はそもそも「文字」という概念がないのです。
そこで、ひらがなを形で認識してもらおうと考えました。

猫を見て→「ねこ」
あを見て→「あ」という名前のものって覚えてもらうってことかな
そう、
「あ」を見せて、これは「あ」だねって教えてあげたんだよ
絵本を読みながら文字を見せて、声かけをしていました。
これは3歳ごろからスタートした記憶があります。
ひらがなのおすすめ絵本と遊び
見せる絵本はわかりやすそうな、優しいイラストのものを選びました。
大きな文字+イラスト、このタイプの2冊を購入(著作権の問題で中身が見せられないのが残念です)。
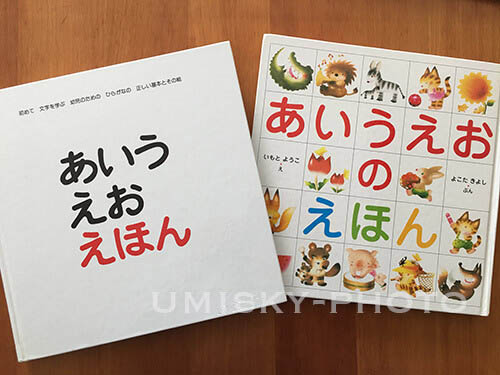
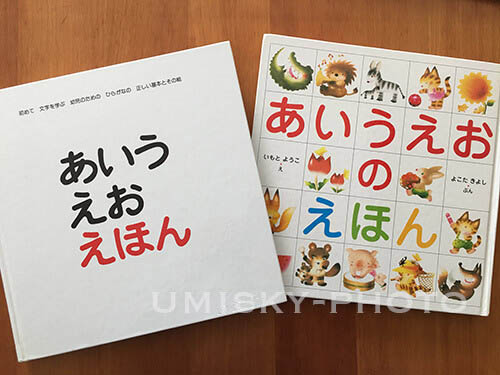
名前がとても似ています!
- ひらがな+イラスト→あいうえおえほん(左)
- ひらがな+物語→あいうえおのえほん(右)
イラストや文章と合わせて、覚えやすい内容となっています。(例えば動物の名前や、道具の名前など)
あいうえおえほん
まず初めに選んだのは【あいうえおえほん】
はっきりしたイラストと、大きな文字が特長
物、名前というシンプルな構成で、子どもはずっと見ていました。
「これは何かな?」「そう!当たり〜!!」と声をかけると、やる気になってくれます。
あいうえおのえほん
こちらは優しいタッチ、いもとようこさんが絵を描いている【あいうえおのえほん】
いもとようこさんは、抱っこが題材になっている「宿題」という絵本でも有名
こちらはページごとの短い物語になっています。
子どもでも理解でき、何度もリズミカルな音が出てきます。耳に残りやすいので、一緒に読めるようになりました。
繰り返し読めるのはこっちでしたね。
かるたは脳の記憶力アップにも良さそう
そして絵本を楽しめるようになり、次に手に入れたのはかるた。3歳半ぐらいでした。
一目惚れのぐりとぐらの【かるた】を購入。
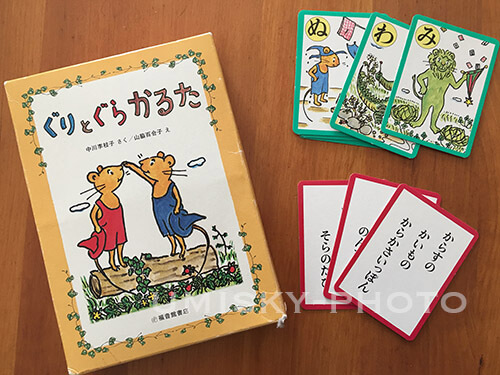
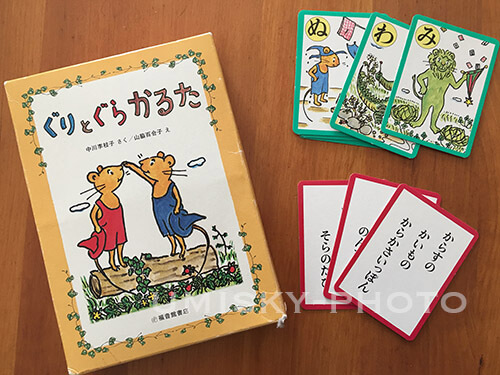
可愛いよ!クスッと笑えるような読札も良いんだよ〜
韻を踏む、リズミカルな読札が特徴です。
暇さえあれば「かるたする〜」と言うほど、ハマっていました。
- 文字の認識は低め
- イラスト+文章を覚える
- 文章を丸暗記
- 文字だけで取れるようになる
遊ぶごとに記憶力が良くなり、大人も負けることがありました、
かるたは100均にもありますが好きなキャラクターは何と言っても食い付きが違います!
お子様の好きなキャラを、ぜひ取り入れてみてくださいね。
楽しく遊びながら自然と身につけると、文字だけではないところにも良い影響がある気がします。
ひらがな、カタカナカードで読む練習をする
かるたで読めるようになったあとは、ピクサーの【ひらがな・カタカナカード】を購入。
- 赤/青
- ひらがな/カタカナ
で分かれています。
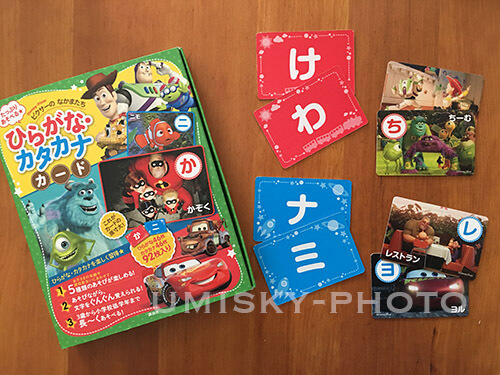
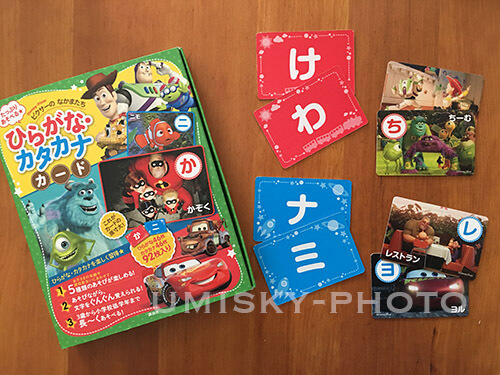
このカードは、かるたのような読札がありません。自分で読む文章を考えて遊びます。
- イラストから→文字を選ぶ
- ひらがなを見て→カタカナを選ぶ
- トランプの神経衰弱のようにも遊べる
ピクサー映画を見ている時にカードを思い出したり、記憶を連動させることもできるようになっていきました。
ポスターを貼っておく
子どもがいる家庭ではけっこう見かける【あいうえおひょう】
我が家はおさるのジョージでした。
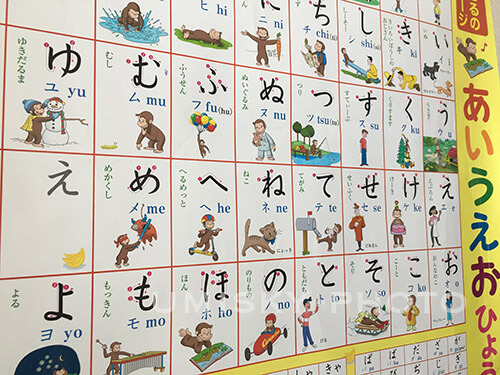
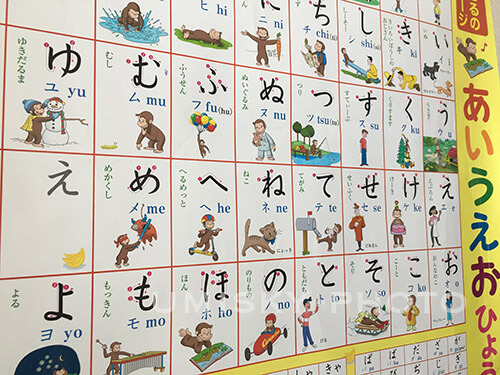
これもさりげなく貼っていましたが、ずっと見向きもしなかったです。
しかし、かるたを覚えたら「なんて読むの?」と質問してくるようになりました。
そのうちに濁音も読めるようなっていくから不思議です。
ここまで読めるようになったらひと段落して、入学準備に取りかかれそうですね。
とにかくキャラものは最強
読めるけど書けない
のんびりペースでやっと読めるようになった!
でも、字は書けないんです。
読み書きはセットかと思いきや、そうじゃないんですよね。
- 濁音・半濁音の判断が難しい
- 読めても、書けるわけではない
字を書くという概念もまだないんです。
上の子がいると覚えが早いけど、一人っ子はのんびりかも
やはり書くことで覚えていくのが一番だろうと思い、書く練習に選んだのはスマイルゼミ【幼児コース】です。
スマイルゼミの様子はこちらの記事に書いていますが、他の力も総合的につけていきたいところですよね。
ある程度ひらがなが読めてくると、本人も楽しくなってきますから、やる気に期待しつつ親はマイペースに見守っていきましょう。
練習はのんびりで大丈夫
生活の中に文字は溢れているので、そのうち自然と覚えていきます。
- 形としての認識が高まる
- 文字や、文章を読む
- 読めると楽しくて、もっと読む
- ひらがなに似たカタカナも読めるようになってくる
今は読めなくても、半年〜1年前と比べて成長していればOKとしましょう!
できないことに目を向けるより、できるようになった事に目を向ける
大人が思う以上に子どもは、文字を読む楽しさを、自分なりに身につけていきます。
疑問があれば、そのつど答えてあげるだけで十分サポートになるので、焦らず、学んでいく姿勢に寄り添っていきましょう。